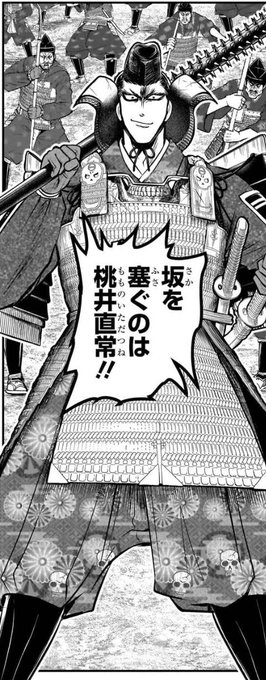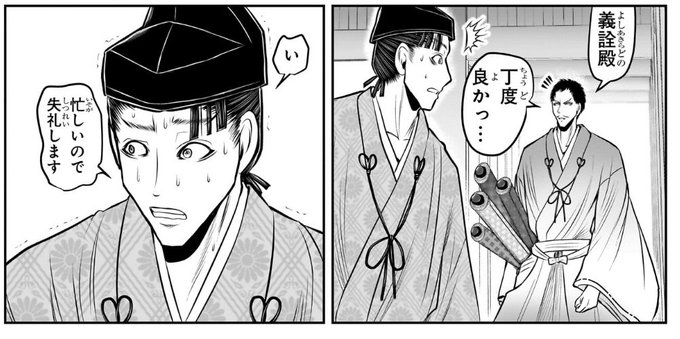逃げ上手の若君のTwitterイラスト検索結果。 1,179 件中 4ページ目
なお、頼継の改名は立直の度に行われたと考えられます
諏訪大社大祝は神の依り代である以上、諏訪外部に出向いて戦の穢れにまみれることが許されませんが、頼継は積極的に諏訪の外で戦をしたため、その都度改名して穢れを清める必要があったのです
#逃げ若 #逃げ上手の若君
https://t.co/9xAFu1PhWu
12
35