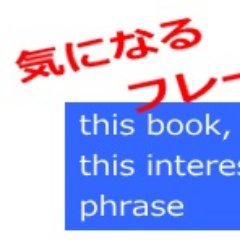3 件中 1〜3件を表示
#ヤマザキマリ◆#たちどまって考える 2020.9/中央公論新杜
社会という群れのなかでなければ生きられず、知恵の発達した生き物としての傲りで膨れ上がってきた人類。
パンデミックは、そんな我々にいったんたちどまって学習する機会を与えてくれた。
0
0
★吉村喜彦『バー・リバーサイド/二子玉川物語』は、洋酒とつまみのマリアージュの連作短編集。ほんとに美味そう。小さなバーの店主(60歳)は元大学助手。「この歳になってわかったんですが、信じられる人なんて、ほんのわずかですよ」。常連客はかつて挫折したり、いま怒りや焦りをかかえたり…。
0
0
あけぼののうそにつまずくさくらかな・千代尼、これでこそ命をしけれ山ざくら・智月、かかるとき人や死ぬらんちるさくら・星布尼など女性俳人の句をまとめた別所真紀子『江戸おんな歳時記』。女性俳諧師が多数いて句集を出す江戸文化は類を見ないと。
0
1