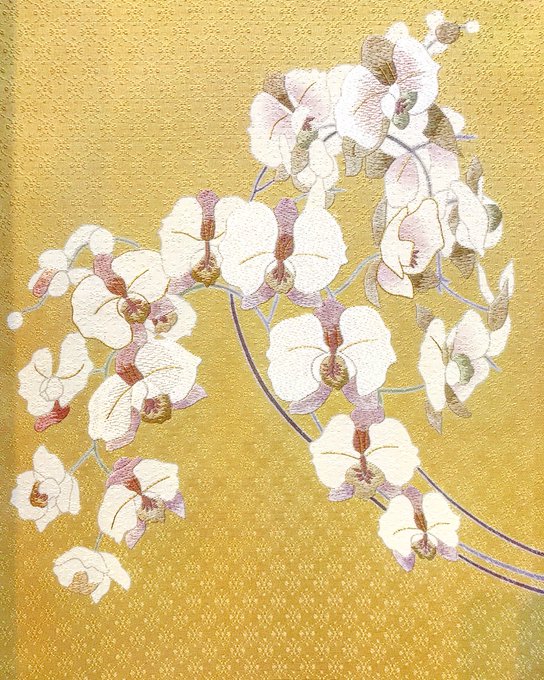きもの文様のTwitterイラスト検索結果。 65 件中 3ページ目
きもの文様 1227
上溝桜
上溝桜の名の由来は、古い時代からこの木の材の表面に溝を掘って亀の甲羅を焼いて亀甲占いに使用したことから「上溝(うわみぞ)」から「ウワミズ」に転訛したというのが通説です。
さらに花の後になる赤い実は果実酒になります。不老長寿の薬酒として珍重されたそうです。
きもの文様 1186
朝顔文
朝顔は平安時代に薬用として、中国から伝えられたといわれ、その種を下剤に用いたとされています。
江戸時代には観賞用として、さかんに作られるようになり、櫛や手ぬぐい、団扇の文様として登場します
一朝一期の花だから美しいととるか、儚さや無常を感じるかの違いですね
きもの文様 1155
カルタ文
カルタは、室町時代末期に、ポルトガル人より伝えられたり遊戯具で、それを模して国産の天正カルタが作られた。
この時期、新種のカルタが趣味性豊かに考案され、その絵柄の多様さにより、カルタもまた文様となった。
新しい遊戯具との新鮮な出会いによって文様化がすすんだ
きもの文様 1128
辻が花文
室町末期から桃山時代にかけて現れた、絞り染めを基調とした模様染めをいいます。
草花を図案化し、白、茶、紫、藍を主体に絞り染めと墨ざしによる繊細な描き絵や刺繍、さらに図柄を透かし彫りした型紙を使って布地に糊をつけ、その上に金箔を押したものもある。
きもの文様 1122
月下美人
夜、しかも一晩だけしか花を咲かせないことが特徴です
花言葉
はかない恋
繊細
ただ一度だけあいたくて
快楽
はかない美
あでやかな美人
強い意志
秘めた情熱
やさしい感情を呼び起こす
などです。
「美人薄命」という言葉は、
月下美人から由来しているともいわれている
きもの文様 1048
薔薇文
中心円を放射状に取り巻く花弁を、正面から見た形そのままを文様化した図柄や、意匠デザインした図柄もある。
薔薇の伝説はギリシア神話に始まる。
「Rosa」は、古代ギリシア語でバラを意味する「rhodon」やケルト語で赤色を意味する「rhodd」が語源であるといわれます。
きもの文様 1006
花筏文
丸太や竹などを並べて藤蔓や縄でつなぎ合わせて水に浮かべたものを筏という。
筏は船の通れない渓流などで主に木材の輸送に用いられている。
筏流しに桜などの花、折枝を添えたものを花筏という。
#花筏文 #きもの文様 #FLOWERRAFT
きもの文様 979
梅文様
厳しい冬に花を咲かせ、いち早く春を告げる梅は、竹や松とともに並び称される吉祥文様でもあり、寿ぎの思いを込めた装いにもぴったりです。
梅の毎の文字は母親を表しますが、厳寒の最中、香り高き花を咲かせる梅の姿は、まさに子を産み育てる母親の強さ、尊さに重なりますね
きもの文様 970
鬼三味線
目には酒 耳にはやさしき三味の音に ひかれてさらに鬼と思はず
一口にとりてくふのは目にも見ず 三味線かじる鬼ぞおそろし
聞くままにひかれこそすれ 三味線のおともかもなき 身をしらざれば
酒や遊興の類は、鬼に喰われるように身を滅ぼすという教え
きもの文様 968
『女虚無僧』
顔を完全に隠した虚無僧の図ですが、その華奢な指先や少しだけ覗かせる足先から美人画とわかります。
春画のようなジャンルには決して筆を染めなかった大津絵ですが、美人画自体は非常に多種多様に渡って存在し、中にはこういった一風変わった絵もあります。
きもの文様 951
葡萄文
葡萄は実りの様子が豊穣や多産を意味するとされ、五穀豊穣、子宝祈願のしるしとして貴ばれた。奈良時代には既に染織裂などの遺品が数多く見られ、陶器の絵柄にもなっています。
日本で葡萄が栽培されるようになったのは平安時代以降で絵画的に表現されるようになった。
#葡萄
きもの文様 937
霞文
霞のたなびくさまを全面に地紋のようにあらわした図柄や、ぼかしや模様の区切りなど、きものの模様を構成する上で、なくてはならないものです。
実際には形のない霞を日本では万葉の昔から空中のさだかには見えぬ水気をさすものという概念により日本的な感覚で文様に描いている
きもの文様 883
面文
芸能に用いられる諸用具をきものの文様に取り入れることは古くから行われていたが、面や冠り物を写真的に写して文様とするのは、ごく近代のことである。
能面は役によって面が違い、人物設定や喜怒哀楽を暗示する。その面を文様として身につけることで自身の気持ちを託す意味も