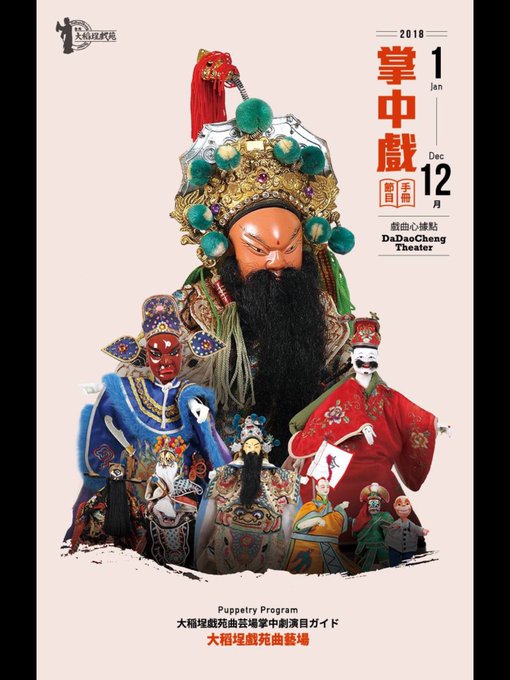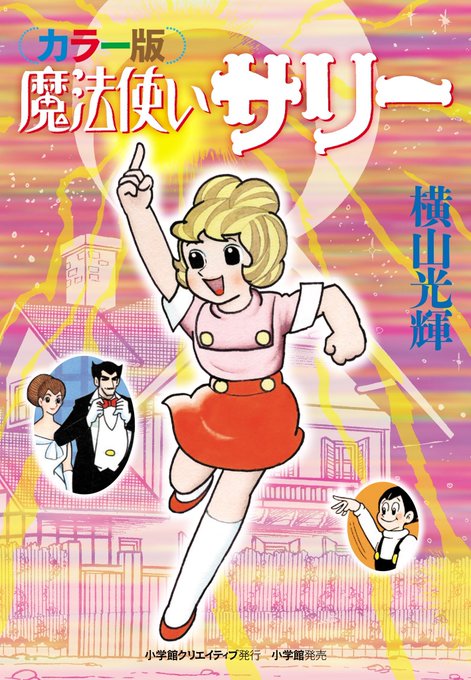74 件中 61〜70件を表示
また、京劇《無底洞》では、鼠の妖怪と闘います
その時に天界から助っ人に呼ばれるのが「猫神」です
鼠退治のスペシャリストって訳ですね
1
6
八仙の中のお一人、張果老
この仙人の持つ法宝“魚鼓”…曲藝(中華圏では語り藝の事)に遣われる楽器の一つです
…“魚鼓”ではソレらしいのが見当たりませんが“竹琴”で探すと同じ形態の物が出て来ました
竹筒の底に皮が張ってあり叩き、二本の竹で拍子をとって唱い語る藝だそうです
10
23
#自分を作り上げた漫画4選
オバケのQ太郎
じゃりン子チエ
クシー君の夜の散歩
朝日ソノラマ 水木しげる師シリーズ
…シリーズって括りじゃ無かったですねぇ?
0
4
5月12日大稻埕戲苑(永楽市場8階)
14:00〜
陳錫煌傳統掌中劇團公演《桃花山》
この時期、臺北にお出掛けの方ぜひご覧になって下さいませ!
4
8
臺北での古典布袋戲公演のご案内…
大稻埕戲苑 迪化街永楽市場8階
5月12日 《桃花山》陳錫煌傳統掌中劇團
5月26日 《烏盆記》臺北木偶劇團
この時期、臺北にお出掛けの方、是非お遊び下さいませ‼️
11
16