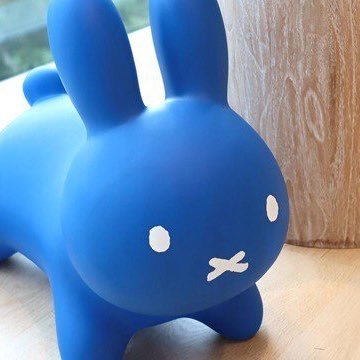オランダのデン・ハーグのマウリッツハイス美術館で、米ニューヨークのFrick Collection所蔵のオランダ黄金期の絵画10点を紹介する企画展“Manhattan Masters”。目玉はレンブラントが破産等で苦境にあった1658年の自画像と背景の地図が印象的なフェルメールの「士官と笑う娘」。
吸血鬼、マドンナ、憂鬱、赤と白等の諸作品、星月夜、桟橋の上の少女達、晩年のパトロンであるマックスリンデ邸や現オスロ大学の記念堂の装飾プロジェクトへの提供作品まで画家の全画業を網羅的に紹介。2023年1月22日まで。
Santiago de los Espanoles 教会内のHerrera家礼拝堂のフレスコ装飾を依頼され、工房の画家と共同で製作に当たった。その後、同教会の運営が困難になり、完成作品は19のパーツに分離され教会外に搬出されたが、本展では、うち7つを保管するプラドが他のパーツを集結させ、当時の素描等も交え、今はなき
位置付けられてきたその少し前の時代の動向に光を当てる貴重な展覧会(後にGroup of Sevenのメンバーとなる画家やカーの作品も本展に出展されているが、既にポスト印象派、フォービズム、アールヌーボ寄りな傾向で印象派からの距離が感じられ本展のテーマの次を予感させる。)。
が好んだ主題そのものだ。本展では画家の作品とロココ期の作品を比較展示しその影響関係を明らかにする。雅宴と一見関係なさそうな静物画もしっかりロココ期の静物画の第一人者シャルダンの影響を受けているというのは意外。
また、両者は共に自前の美術館設立を構想していた。慣れ親しんだ西美のモネ「船遊び」、マネ「ブラン氏の肖像」、ゴーガン「ブルターニュの少女達」、ルノワール「ハーレム」、シニャック「サント=ロペの港」等が遠く離れた異国でフォルクヴァング所蔵作品と混ざって展示されている姿は何とも新鮮。
最終章では、斬首等の絵的に共通する場面の多い神話「ダビデとゴリアテ」「サロメ」との類似性を探る。展示室内の作品がどれも斬首のシーンという光景は、悪夢が繰り返されるようでちょっとホラーだが、同じお題でありながら画家ごとに異なる描写の背景を考えると面白い展覧会。
同美術館は1900年にHenry Vaughan氏から38点のターナーの水彩画の寄贈を受けたが、寄贈の条件として、毎年1月(限定)に寄贈作品を無料で一般公開することが遺言で課せられていた。これを受け、同美術館では1901年以降、年初に「Turner in January」を続けている。
本展では、若きコンスタブル(作品左)のキーパーソンとして同郷の大家ゲインズバラ、ゲインズバラを手解きした同郷の先輩画家George Frost(右上)、身分の差を乗り越え友人関係にあり、息子が後に彼の助手となった画家John Dunthorne(右下)、地域社会のパトロン的存在のElizabeth Cobbold等を紹介する。
作品にもモデルとして登場したことのある妻Mariaの死(1828)がコンスタブルの画風の変化に影響を与えたとのこと。本展の目玉作品「Hadleigh Castle」の荒涼とした風景も初期の作品とやや趣が異なる。今春の三菱1号のコンスタブル展とは違ったコンスタブルが見られる展覧会。