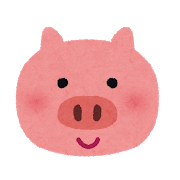『公衆作法 東京見物』(1926 大正15・昭和1)
こうした迷惑行為を見た紳士2人が、ヒソヒソと会話する。
「もう少し共同観念に目ざめてほしいな」
「そうだ。少し共同観念を加味してくれるといいのだ」
まだマナーという言い方がないため、「共同観念」を「加味」、と表現するのがちょっと面白い。
『貸間あり』見どころその2。
キャバレー?で踊る和装ダンサー。吉原つなぎ(廓つなぎ)の浴衣に半幅帯、イヤリング、裸足、と今なら叱りとばされそうな姿で、太もももパンツも丸出しで踊りまくる。ほんの数秒だけど印象的。
録画したBSフジ「人生宝談~人間国宝と語る」を見たが、素晴らしい番組だった!再放送してほしい。
まずは、いつもシブカッコいい長唄囃子方の国宝・堅田喜三久さん。
黒鞄から鼓の胴と皮を取り出し、組み立て、ナメて湿らせた和紙をちぎって皮に2ヶ所貼る! 皮を湿らせて音色を変化させるのだそう。
マコーレーマコーレーカルキンカルキンの話、名前なんか別に何だっていいんだ!な開放感。
昔つぶやいたコレ思い出す笑
https://t.co/sCArfP0InS
タモリ「岡本太郎さんです!」
太郎「あそ、知らなかった」
タモリ「名前なんかどうだっていい….」
太郎「名前なんかあるから、人間は虚しくなるんだ」
中でも素晴らしかったのが、「パエトンの墜落」1604〜8頃 ワシントンナショナルギャラリー蔵。
太陽の馬車で天空を暴走する少年パエトンと、暴走を止めるべくパエトンを雷で撃ち殺すユピテル。落ちゆく馬車、人、馬、そのバラバラな姿態と、画面を斜めにピシッと横切って引き締まる構図。カッコイイ…
このサレジオ教会(碑文谷教会)に掲げられていた「親指の聖母像」(1700年代に来日し幽閉された伊人宣教師シドッチ持参→長崎奉行所蔵→現 東京国立博物館蔵)どこかで見たような…と思ったら、つい先日、国立西洋美術館の常設展で見たカルロ・ドルチ「悲しみの聖母」1655年頃とそっくりなのだった。
上智大学横のイグナチオ教会にて、「オルガンと祈り 〜クリスマスの喜びを待つ」の会。大木麻理さんによるパイプオルガンの素晴らしい演奏で、バッハ『ピエス・ドルグ Pièce d'orgue』という曲を初めて聴いたが、荘厳で華麗で本当に美しかった…。
ちなみに、作者のマックス・ビアボーム(Max Beerbohm)は風刺画家として大変有名で、特に、同じグループで先輩にあたるオスカー・ワイルドを描いた風刺画が…ヒドイ。彼なりにワイルドを尊敬していたらしいけど、ヒドイ。ヒドすぎるが、バナナマンみたいでつい笑ってしまう。
川島雄三『わが町』1956年 昭和31年より。
辰巳柳太郎と南田洋子と三橋達也と菅原通済(このシーンのみ登場)が待ち合わせした場所は、おそらく高島屋の入っている南海ビルディング内の難波駅改札前。
南田洋子の後ろに、高島屋の広告文「全館冷房」「夜7時まで」が。当時は19時まで営業だったのね。