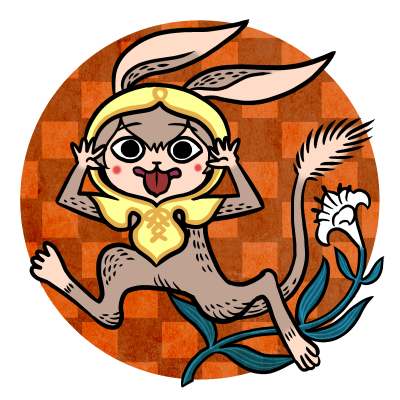写本のTwitterイラスト検索結果。 378 件中 4ページ目
チェコの写本、1420年の『人類救済の鏡』。1頁に2枚ずつの絵でイエスの受難等と鏡を通してそれを世俗に置き換える。ユダがキリストを逮捕させるために接吻する場面は夜のホモたちに、十字架を担ぐキリストと対照の絵は薪運びの少年。イエス復活の鏡は脱獄囚、イエスの黄泉降りvs親しい人々との再会。
#上映時間が150分以上あっても面白かった映画
ヴォイチェフ・ハスが撮った映画。
展開の面白さだったら①『サラゴサの写本』②『人形』
淫靡で豪奢な物質偏愛の饒舌と冗漫にのめり込むなら③④『砂時計』。
ふと気になって写本の絵を調べてみると、格子状の構造物は確認できます(これがどれだけ当時のものに忠実なのかは分かりませんが)
1枚目の格子はもしかして木製? https://t.co/arbS6OBxfn
写本の中で15世紀頃の食事の様子が想像できる。但し古代の出来事も中世、ルネサンスの風景になる。皇帝が大勢の廷臣や使用人を動かし宴会。骨を待つ犬。アレクサンドロス大王のディナー。鳥や魚の描写がリアル。戦場のテントで食事をとるシャルルマーニュ。優雅に踊ったサロメは洗礼者ヨハネの首を得る
鈍器については当時のスペックに寄せた板金鎧と鈍器で検証しないと意味が無いと思います
15世紀の写本を見てもメイスは登場しますし、ブルゴーニュの重騎兵は長剣の他にメイスも携行する事が公の勅令で定められていました
つまり板金鎧が登場しても尚鈍器は有効な武器だったという事ではないでしょうか
ゴシック祭壇画、写本の挿絵、聖書の題材は様々なスタイルで永遠に描かれる。コロンビア出身のフェルナンド・ボテロの描く人物は皆デブだが彼は宗教的絵画も描き'地獄の門'は特に興味深い。ポール・デルヴォーは第2次大戦時ベルギー王立自然史博物館でヒトの骨のスケッチに熱中、独自の宗教画を確立。
最近ときめきが足らない気がする。
装飾写本をだらだら見ているけど、やっぱり、触ってみたい、実物見たい。
それからライブ行きたい。ALIのライブ行こうかな
明日たんたん練習日なのだけれど、本当改めてすごいセトリにしたな情緒どうなってんだよ。笑
そしてこのアー写本当可愛いゆかたんしゅごい(*´꒳`*)
ズボンとスカートにちゃんとマーク入り🐷❤️🐥
『Oldham Rules』
最小限のルールで手早くプレイできる、中世風ファンタジーRPG。中世欧州の装飾写本の余白に書かれた奇妙な絵(例:カタツムリに乗った農民がピッチフォークで角ある小さな悪魔と戦う)にインスパイアされた、世界設定とアートディレクションが売りとのこと。
https://t.co/RN6kQZ5BbX
「アルメニアはキリスト教国となった初めての国」と教皇フランシスがおっしゃったとか。ローマ帝国の方があとなのね。左は1615年に制作された写本挿絵の一葉。右は5-6世紀の柱頭彫刻。
写本に居た、謎のニワトリと騎士……
写本では、騎士が鶏の首絞めてるように見えるけど、私は騎乗(騎鶏?)していることにした!(*゚▽゚*)
←My work. Manuscript →