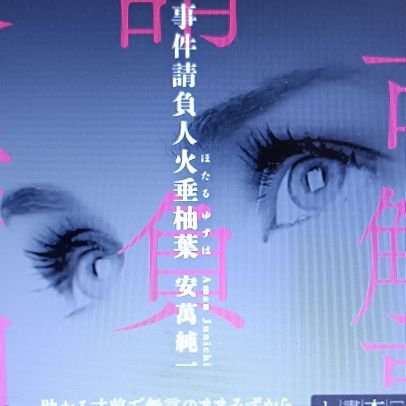「もう新しい(推理小説の)トリックのタネは尽きた」などという言動を見たり聞いたりされた方もいらっしゃることでしょう。そういうのは「もう新作手品など作れない」「新しい曲など作り得ない」などと一緒で、作らない人の妄言(もしくは言い訳)だと思います。まったくそんなことはございません。
【滅びの掟:6月1日発売】トリックに関してですが、私は二種類の分け方で考えています。ひとつめは物理トリックと人文トリック。人文というのは錯誤、錯覚といった心理的なものと、人物入れ替わりのようなものも含みます。複数のトリックを使う場合、この両者が出てくるのがバランスよく感じます。
忍者というものは受けた命令に疑問を抱かず遂行するべし。しかし忍びとて人の子。主人公の忍者は、自分たちがなぜ戦わねばならないのか疑問に思い独自に調べ始めます。江戸詰めの仲間に秘密の手紙を送り、徐々に陰謀の姿を露わにしていくのです。
忍者たちが忍法とトリックを用いて戦う。それが順番に出てくるだけではしかし、ストーリーがあまりに平板なものになってしまいます。そこに絡んでくるのが背後にうごめく陰謀です。これには当時(家光の時代)の社会が色濃く影を落としています。
忍者同士の対決となれば忍法と剣法が使われるのは当然ですが、副題に『密室忍法帖』とあるとおり、この作品ではそれらに加えて密室トリックなどの推理小説的トリックが数多く登場します。自らが生き延び、相手を倒すべく、忍者たちが必死でそれらを考案、駆使しながら死闘を繰り広げていきます。
以前にも短編を書きましたが、推理小説的トリックと忍者との相性は非常にいいと思っています。忍者にはもともと、普通の人にはできないようなことをやったり、奇抜な発想で相手をだましたり出し抜いたりするところがあります。トリック創案者として無理がなく、まさにぴったりな存在です。
なぜ忍法帖と本格ミステリーを組み合わせたのか。どちらも大好きだったので、一緒にできないものかと考え続けていました。ミステリー要素を持った時代小説は多々存在しますが、トリックと忍者を組み合わせたものが見当たらないことも、やってみようという動機につながりました。
「本日、印刷始まりました」というメールをいただきました。いままでそんなメール受け取ったことあったっけ。なんかロケット発射のカウントみたいでスリルを感じる。今回はいろいろと、デビュー直後に戻ったような初々しい気分。