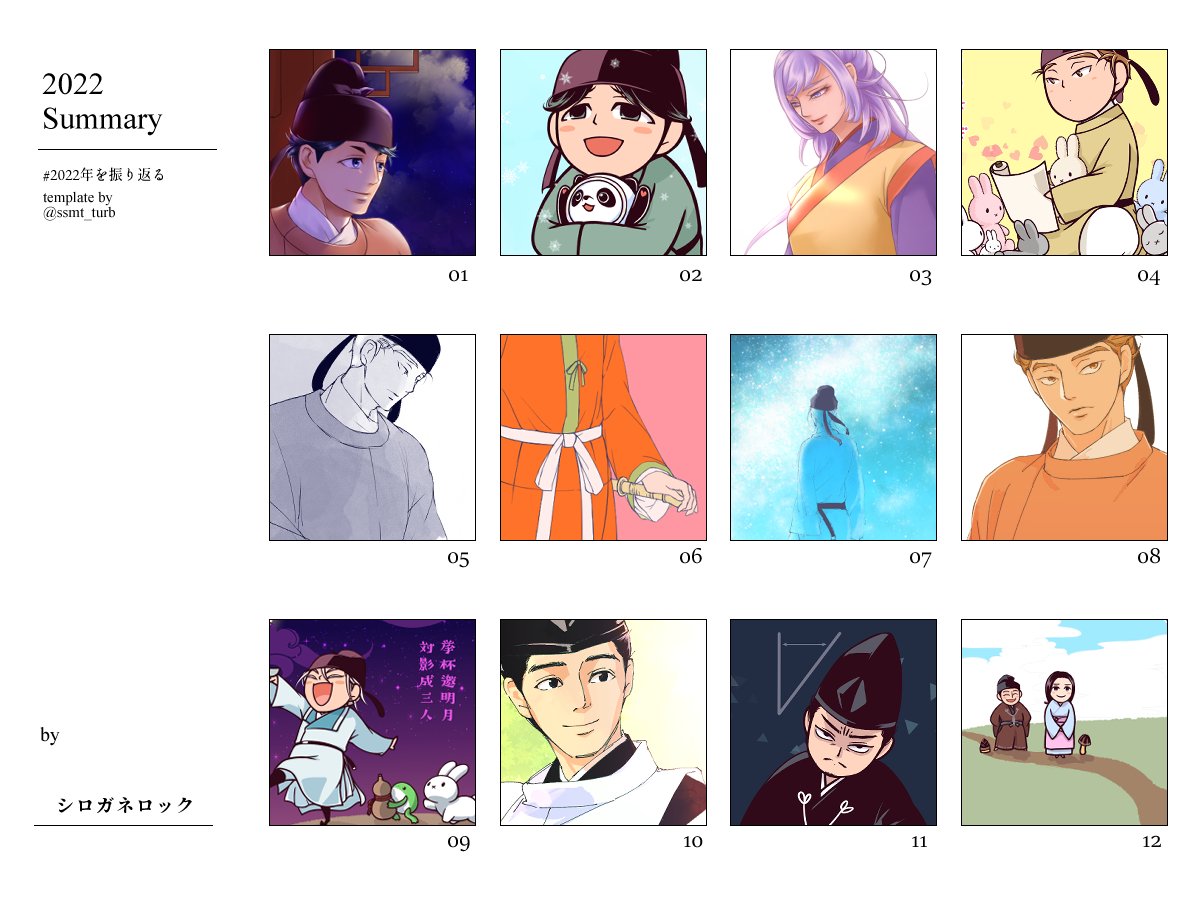1,777 件中 841〜850件を表示
タグお借りして、結構前にやろうと思ってたやつ。
10月の実朝以降殿絵ばかりになってしまった…
そしてそれ以前も自分で思ったよりデフォルメが多い。
ドゥンて今年だったんだねえ…
#2022年を振り返る
7
69