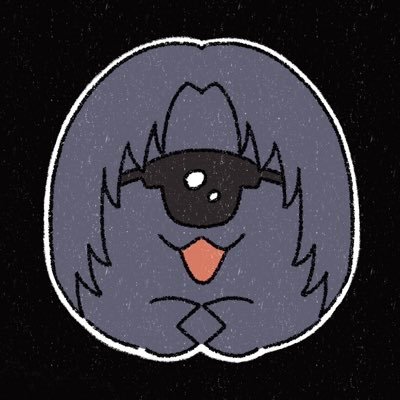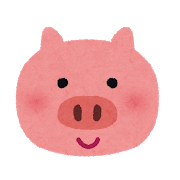下北半島と津軽半島のヴィジュアル・アナロジーとして、マサカリで人間の頭を叩き割る『罪と罰』的風景を寺山修司が青森県に幻視したのはあまりに名高いが、山形県なんて形がモアイ像ですからね。不思議ではあるが、文学にはならない。
【緊急速報】
『ミュージック・マガジン』と『レコード・コレクターズ』の2月号に『ゴシックカルチャー入門』の書評が掲載されました! 前者では野中モモさんが前書き「暗黒批評宣言」の「ショーマンシップ」を、後者では村尾泰郎さんが拙文の高山宏的なる「饒舌な語り口」に注目くださってます!
「光明編集者」(初出:キネ旬2019年3月下旬号の近況欄)である寺岡裕治さん編集の『映画はどこにある インディペンデント映画の新しい波』(フィルムアート社)もわが単著同様にnuデザインではないか!
町田で開催中の「THE BODY―身体の宇宙」展のトップ画に選ばれたホルツィウスのヘラクレス像だが、『すばる』創刊号の伝説的マニエリスム特集で碩学ダゴベルト・フライが分析していた。順光ではなく逆光で描かれているこのヘラクレス像を「正しく」見ているのは我々ではなく、画面奥の二人という捻くれ
今日は前川ひな個展『Double Dweller』に行ってきた。イェイツ「記憶術」を自身最大のテーマに掲げる前川画伯のガイド付きで、そのヘルメス的/人類学的/サイケデリックな綺想の数々を堪能。「母」が大きなテーマとのことで、少しだけ謎が解けた気もする(個人的なご依頼にもOK下さった。感謝!)
「ララランドと青の神話学」を書く上で、ミシェル・パストゥローの『青の歴史』には大いに助けられたのだが、残りの色彩シリーズである『Red』『Green』『Black』が未邦訳なのは悲しい。心ある版元があれば翻訳してもらいたい(英訳版は想定も素敵だ) https://t.co/MvHhLxkjHk
翼を広げれば三百万里に達し、那羅延天という力士を乗せて宇宙を飛び回るガルダという神話上の巨鳥がいる。モンゴルの力士はこの鳥にあやかって両手を翼のように広げパタパタさせながら闘技場に入場する。日本の力士が掌を打ち合わせた後に両手を広げる仕草は故にガルダのスピリットを召喚する名残り。
なんでしょ、武井武雄(左)が「腐る」とスワンベルク(右)になる印象。そうすると児童雑誌「コドモノクニ」の武井武雄の挿絵を見ていた澁澤龍彦が、後年スワンベルクを好きになる感じ分かる。