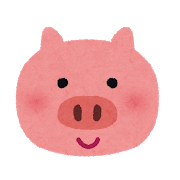953 件中 151〜160件を表示
@animesama @kakitama 衝撃度でいうと地味にここらへんも挙げておきたいですね。今見るとかえって当たり前ですが、当時は「アニメにはこんなすげえ奴らがいるんだ」「アニメからはこんな新しい表現も出てくるんだ」とビンビンに主張してた気がします。
15
40