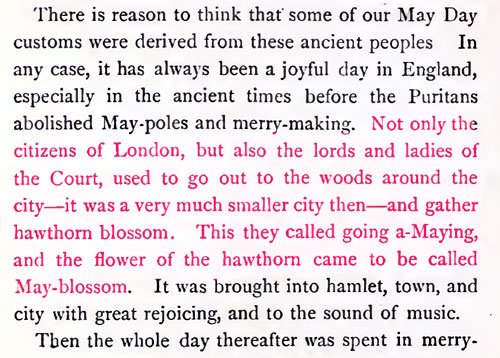さてメイデイ。文献によれば昔は五月一日にロンドンの庶民も貴族も近郊の森に遊んで hawthorn サンザシの花を集めて持ち帰ったとか。この風習 "go a-Maying"「さつきあそび」は十九世紀には廃れたとのこと。こういった懐古が世紀末オカルト復活につながるわけです。
英国の子供部屋にはなぜか海賊が出没します。英国児童たるもの一度はカリブ海でスペイン船を襲わねばならないとする暗黙の了解があったようです。魔術儀式の原点が幼児期の「ごっこ」にあるとすれば、海賊ごっこの魔術的意義は?などと考察するのも一興かと。絵はグリーナウェイ。
ついでに英訳「桃太郎」をもうひとつ。テレサ・ウィリストンの『日本童話』(1911)ではキビダンゴにやばい成分が含まれていたと解釈できるようです。普通の動物が狂戦士化しています。絵は小川三知。
雑。昆虫を擬人化すると妖精になる、と安直に考えてもよいのかもしれません。虫の生態の観察研究が進むと、そこで得られた情報が妖精世界に適用されていきます。妖精糸で編まれる繭が揺り篭になったり棺になったり。図版は『蝶のお葬式』(1807)から。
猫の雑。十九世紀初頭からのグリマルキンの活躍には目を見張るものがあります。これは象さんの舞踏会に招待されドレスアップして登場したときの図版。猫の社交界の有名レディーといったところか。こうして情報を集めていくと、やがて向こうもこちらに気づく、というのがお約束であります。
今年もまた3月1日「聖デイヴィッド」祝祭日が到来。今回はウェルシュ・ハープに注目。古代ドルイドの教えは吟遊詩人たちが伝承してハープの調べとともに語り継がれた、とロマンチックに考える向きもあります。ハープの構造に古代の密儀が読み取れるといった発想も面白いのです。
同じくゴブルが描く「羽衣伝説」(1910)。確かにそういう非道な話だった、と改めて気づかされました。なおこの羽衣は謡曲ベースのストーリーのため、漁師はすぐに羽衣を返し、天女はお礼の舞を舞って去っていきます。ストーリーの印象のままに絵筆を走らせるゴブルの面白さよ、と。
冬に咲くスノウドロップは可憐な白い花。しかしその意味は希望あるいは凍死という両極端。白い衣は花嫁衣装か経帷子か。十九世紀中頃から大流行する「花言葉」は植物に託す願望にして呪詛ですから、オカルトとの相性は抜群だったのであります。
タロットの雑。昨晩考察したブラダースティック。現代日本で相当物をさがすと、ハリセンよりはピコピコハンマーのほうが近いか、と。緊急時、魔術道具としてエア系魔物の召喚に使用できるかもしれません。呼ばれたほうもショックが大きいと思われます。
近代西洋魔術にあって月の女神は最重要ポジションを占めていて、各国よりさまざまな女神様がロンドンに留学していたといっても過言ではなかったのです。ちなみに日本からは「カグヤ・ザ・ムーンメイドン」が派遣されていた模様。図は1910年にゴブルが描いたカグヤ。