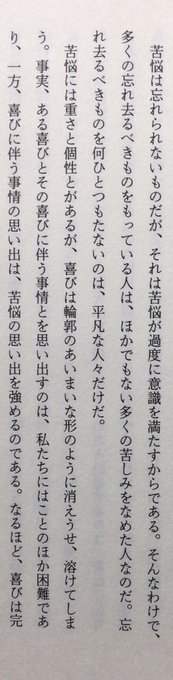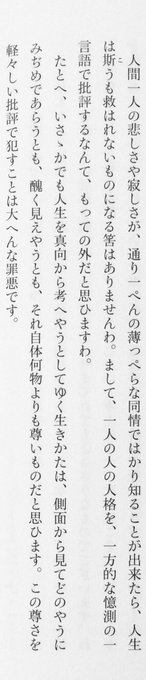「刺身や寿司を食べるとき、通ぶって「素材の味を楽しみたいから、醬油はつけない」という人がいる。個人の好みにケチをつけるつもりはないが、本当に素材の味を楽しみたいなら、むしろ少量の醬油はつけた方がいい。」(小倉明彦『お皿の上の生物学』角川ソフィア文庫、P147)
「本を買うということは、その本を「未来に読む」というひとつの約束のようなものを買うことだった。借りてきた本には期限がある。そうなると、そこにあるはずの「未来」が、あまりに短くてがっかりしてしまう。一方、自分のものにした本には、限りない「未来」が含まれていた」(『金曜日の本』P71)
「ぼくはせめて、小説『火垂るの墓』にでてくる兄ほどに、妹をかわいがってやればよかったと、今になって、その無残な骨と皮の死にざまを、くやむ気持が強く、小説中の清太に、その想いを託したのだ、ぼくはあんなにやさしくはなかった」(野坂昭如『アメリカひじき・火垂るの墓』新潮文庫、P270)
「苦悩は忘れられないものだが、それは苦悩が過度に意識を満たすからである。そんなわけで、多くの忘れ去るべきものをもっている人は、ほかでもない多くの苦しみをなめた人なのだ。忘れ去るべきものを何ひとつもたないのは、平凡な人々だけだ。」(E・M・シオラン『絶望のきわみで〈新装版〉』P167)
3月11日は作家・石牟礼道子の誕生日
「人間一人の悲しさや寂しさが、通り一ぺんの薄っぺらな同情ではかり知ることが出来たら、人生は斯うも救はれないものになる筈はありませんわ。まして、一人の人の人格を、一方的な憶測の一言語で批評するなんて、もっての外だと思ひますわ」(『道子の草文』P56)
「寝室における住み手の行動は、いつも自身の内発性にのみゆだねられている。そうなると遠からずタガが外れる。行き場のない荷物はとりあえず寝室に突っ込んでおけという気持ちを、自分にやすやすと許すようになる。」(藤山和久『建築家は住まいの何を設計しているのか』筑摩書房、P65)
「本を買うということは、その本を「未来に読む」というひとつの約束のようなものを買うことだった。借りてきた本には期限がある。そうなると、そこにあるはずの「未来」が、あまりに短くてがっかりしてしまう。一方、自分のものにした本には、限りない「未来」が含まれていた」(『金曜日の本』P71)
「自分自身の死を内的必然性として誇らしげにおのれのうちに抱えているのは、音楽の調べのみだ。ただし音楽は存在ではない。すべての存在者は理由もなく生まれ、弱さによって生き延び、出会いによって死んでゆく。」(ジャン-ポール・サルトル著、鈴木道彦訳『嘔吐 新訳』人文書院、P222)
「健康人とは、たぶん、基本的に「気の晴れている人」のことではないかと思う。たまに気がふさぐことがあっても、いつか知らぬうちに晴れている。本人がそれを意識できない。基本モードが、晴れなのである。したがって気晴らしについては面倒がない。」(山村修『気晴らしの発見』大和書房、P186)
「一般的には、親や社会に都合のいいことが長所で、都合の悪いことが短所だとされてしまっています。けれど子どもが幼いときから自分の気持ちを抑え、我慢をするのは立派なことに見えるけれども、実は自分を見失うことでもあるのです。」(佐々木正美『子どもの心の育てかた』河出書房新社、P69)