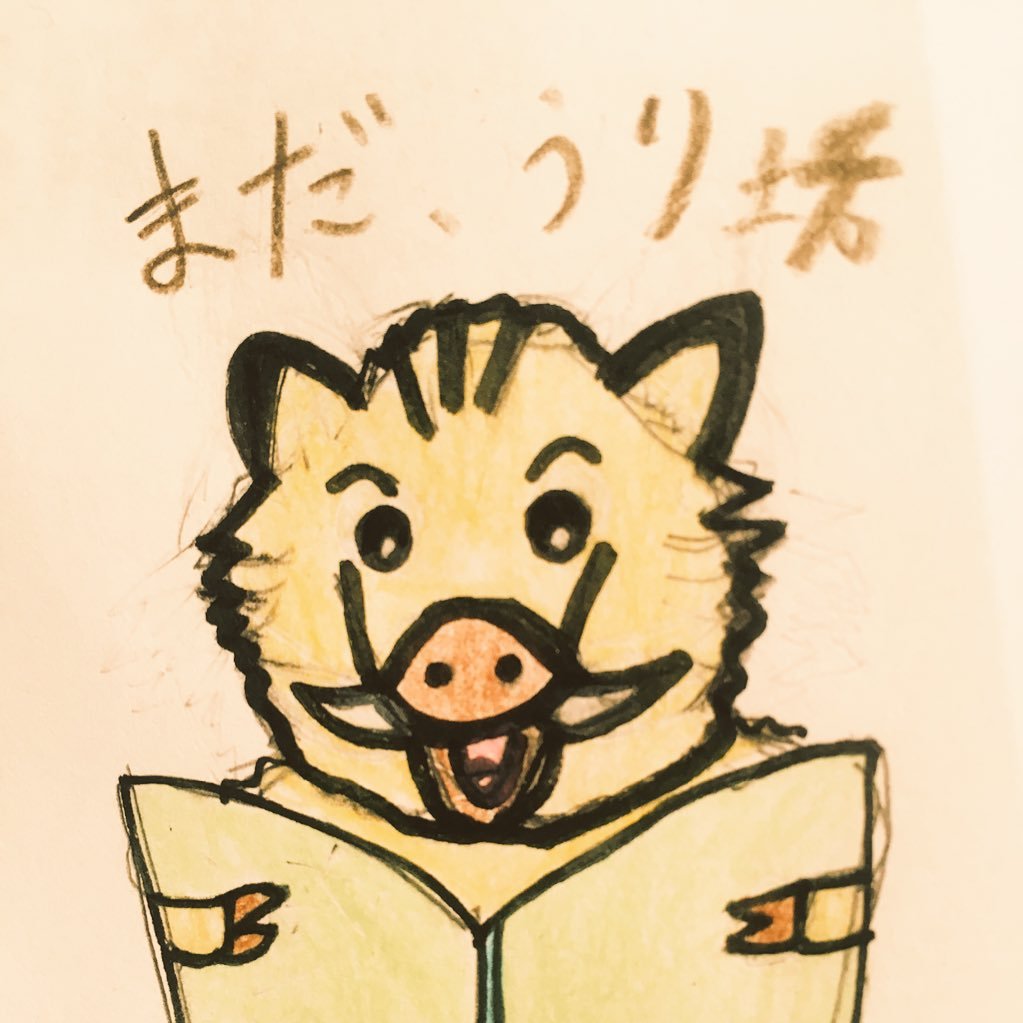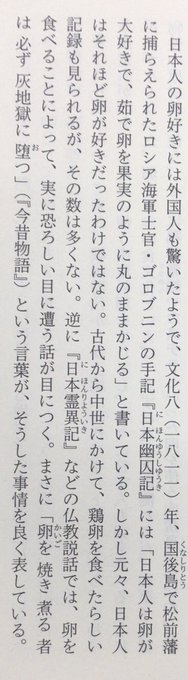「自然に煽られて競争に明け暮れることはどこか空しい。そんなにまでしてどこへ行こうとしているのか。生物の場合でもそうなのだから、科学技術を用いて超高速進化の道を走っているヒトという種、つまり人間の場合はいよいよ空しい。」(池澤夏樹『科学する心』角川ソフィア文庫、P238)
1月20日は、詩人・西脇順三郎の誕生日。
「シムボルはさびしい
言葉はシムボルだ
言葉を使うと
脳髄がシムボル色になつて
永遠の方へかたむく
シムボルのない季節にもどろう
こわれたガラスのくもりで
考えなければならない」
(那珂太郎編『西脇順三郎詩集』岩波書店、P324)
「いたい目にあうごとに、わたしは、自分のえりくびをつかまれて、真理のほうに向けられる。真理は、痛い方角にある。しかし、真理は、方角としてしか、わたしにはあたえられない。思いちがいに思いちがいをついで、その方角に向うのだ。」(鶴見俊輔『不定形の思想』河出文庫、P469)
「元々、日本人はそれほど卵が好きだったわけではない。古代から中世にかけて、鶏卵を食べたらしい記録も見られるが、その数は多くない。逆に『日本霊異記』などの仏教説話では、卵を食べることによって、実に恐ろしい目に遭う話が目につく。」(青木直己『江戸 うまいもの歳時記』文春文庫、P217)
「枠のなかだけで過ごしていたら息苦しくなる。そして枠がつねに正しいとも限らない。そんなときこそアートだ、と思う。アートには、枠をこわして、新たな価値や新たな物の見え方に気づかせてくれる力がある。それは枠の外にいるだれかに暴力を向けるようなものではない。」(『ルビンのツボ』P52)
「世上、人間は四捨五入によって人物判断され、それがその人間の特色として語られますが、捨てられた部分もじつはその人間の一部なのです。「あの人は善人だった」といわれる人であっても、十のうち四つほどは悪であったかもしれません。」(里中哲彦『ずばり池波正太郎』文春文庫、P133)
「カラス類やシジュウカラ類は餌を地中や岩の割れ目などに隠し、後に取り出して消費する貯食行動が知られている。貯食行動には、隠す餌の種類や場所などについての記憶に基づいた取り出し行動がともなうので、高度に知的な行動であるといえる。」(『目立ちたがり屋の鳥たち』東海大学出版部、P180)
「日本人はフジヤマ、ゲイシャ・ガールしか知らない外人をばかにするが、外人向けの日本案内書を作る時、とかく富士山をバックにした芸者の写真で表紙を飾りたがる。また、「横浜」を正しく発音できる外人にも、ヨコハーマという発音を教えたりする。」(ドナルド・キーン『日本人の質問』P22)
「刺身や寿司を食べるとき、通ぶって「素材の味を楽しみたいから、醬油はつけない」という人がいる。個人の好みにケチをつけるつもりはないが、本当に素材の味を楽しみたいなら、むしろ少量の醬油はつけた方がいい。」(小倉明彦『お皿の上の生物学』角川ソフィア文庫、P147)
「自分が人のことを想うほどには、人は自分のことを想っていないのだな、と思う。すねているわけではなく、静かに、そう思う。でも、どこかから僕を見つめて、同じように感じている人がいるのだろうと思いながら、日々を生きる。」(利重剛『ブロッコリーが好きだ。』近代文藝社、P132)