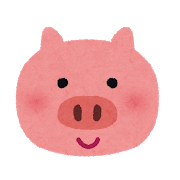【追伸】母親に纏わる言葉を2つほど。「思い知られよ、己が身の、誕生の日は、母苦難の日」と。誕生日は母親が、死ぬ思いで産んでくれた日。自分の事ばかり祝わず、改めて親孝行する日かと。「母死んで、拝む両手があるならば、生きてるうちに、肩1つ揉め」と。親孝行したい時には、もう親がいない。
【追伸】読者が「ロシアや中国が日本の領土を奪う為、戦争を仕掛けてくると思うか、住職」と。「日本の諺に『軒下を貸して母家を取られる』が。『好意に乗じられ、恩を仇で返す仕打ちを受ける』なる意味だが。鍵を掛けず、窓を開けっ放して外出しても、安全な国に住む日本人。お人好しになるわな」と。
【追伸】拙僧の印象だが、信仰してる人の方が「俺がこうなったは『親、社会、学校、会社、先祖のせい。あいつ、こいつのせい』と、何でもかんでも責任を転嫁してる印象が。今の自分を助けているも、苦しめているも、過去の自分の行動。将来の自分を救うも、陥れるも、これからの自分の行動、なんだが。
【追伸】読者が「この戦地経験爺様の怒りに住職は何と答えたの」と。「全くの絵空事なら爺様を『まあまあ』と諫めるが、現にウクライナは、あの通り。ロシアは言いたい放題。有事が起こった後で『何であの時、備えをしておかなかったのか』と後悔しても始まらんかな。被害を受けるは私達の子や孫」と。
【追伸】この男性読者が「主人に黙って妻が実家にお金を使うなんて、なんか嫌ですね」と。「嘘をつかんでもいい夫婦関係を構築してるんなら、黙って奥様がお金を使う事なんてないよ。子供でもそうだよ。嘘をつかんでもいい家庭環境なら、子供は嘘をつく必要がないから、嘘をつかない子供が育つよ」と。
読者男性が「随分以前の法話で住職が『財布は女性が管理するより男性が管理した方が貯金額が多い、の統計が』と法話で。あれって、何故なの」と。「まあ、1つの要因として、女性は実家にお金を使うもんね」「えっ、実家に費やすんですか」「そりゃ、そうでしょ。が、そこは目を瞑らにゃあかんで」と。
【追伸】子育てで最も驚いた話は、知人幼稚園の先生が「2歳の男の子2人が喧嘩を。止めに入ると、片方の男の子が『黙れ、包丁で刺すぞ』と。2歳の子がこんな言葉を知るはずが。恐らく、家庭内でそんな会話が飛び交ってるんだと。迎えに来る祖父母、父母を見ると『なるほど』と、納得させられる」と。
【追伸】わが子が結婚する時に大半の檀家の親が「あんなわがままが、家庭をしっかり持てるでしょうか、住職」と。「心配せんでよか。こういったものは、順送り。結婚し、親になった途端に、自分よりも、もっとわがままな存在(わが子)が目の前に出てくる。自分のわがままは、吹っ飛んでいくから」と。
【法話補足】高校時代、日豊線の〇〇と異名を持つ程の檀家男性が「兄ちゃん(拙僧)。中1の息子が反抗期に」と悩んでお寺に。「君はどの面下げて言ってんだ。中学時代、警察沙汰を繰り返した男が。君に比べたら、可愛いもんだ。自分が未熟だった頃を思い出してごらん。父親なら、どっしり構えろ」と。