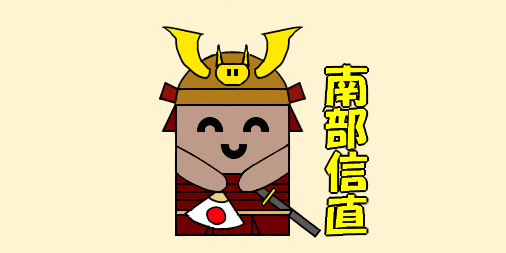陸奥国のTwitterイラスト検索結果。 35 件
二階堂 盛義(にかいどう もりよし)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・陸奥国の戦国大名。須賀川二階堂氏7代当主。
Wikipediaより
おはようございます🌞
今日は【新撰組の日】
1863年(文久3年)のこの日、京都・壬生に詰めていた武芸に秀でた浪士達で構成された新選組の前身「壬生浪士組」に、陸奥国会津藩主で京都守護職の松平容保から「会津藩預かり」とする連絡が入り、新選組が正式に発足した。
良い1日を🎶
狭磯名っていう名前、セッション中は色々出まかせ言いましたけど、元は陸奥国風土記逸文に載ってる土蜘蛛の名前の1つです。データ組んでる時は下位流派土蜘蛛にする予定だったので……といいながら笑顔差分上げとく
⚫︎入内雀(ニュウナイスズメ)
平安時代の歌人・藤原実方が天皇の怒りを買い陸奥国(青森県)に左遷させられた
都に帰れずその地で没した怨念が雀と化し、京都の内裏に侵入し食糧を食い尽くすようになった
故に「入内雀」と名付く
#妖怪シリーズ
<0767 イ…> 岩嶽丸
千年生きて鬼と化した蟹の妖怪。陸奥国の八溝山(福島県と茨城県の県境)に棲む。蟹のような目と耳まで裂けた口、鬼の角、10本の手足を持ち、口から火を吐く。藤原資家により成敗された山賊が鬼神として語られたもの。 朝里樹『日本の鬼大百科』に描かれたイラストが素敵。
#アイギス王国交流会
お姉さんな平山属性クゥイル
長たる偉い平山属性ラキュア
1000年生きてる平山属性アンブローズ
紫ツインテ平山属性メメント
陸奥国府で鎮守府な誰かを思い出してしまうのだ
お題「歌」
歌といえばどうしてもこの人、大伴家持。
歌は海ゆかばで知られる「賀陸奥国出金詔書歌」の反歌から。
大伴氏としての矜持が芽生えたタイミングかもしれない
#歴創版日本史ワンドロワンライ
A.D.802年5月19日、蝦夷の首長アテルイ(続日本紀:阿弖流爲、日本紀略:大墓公阿弖利爲)が、陸奥国胆沢でヤマト政権の征夷大将軍・坂上田村麻呂に降伏し、三十八年戦争(蝦夷征討戦争)が終了。4ヶ月後、アテルイならびに蝦夷の指導者モレ(盤具公母禮)が河内国で処刑された。
まだ松の内ですし!って事で、改めて2021年もよろしくお願いいたします!
むつ描き初め!
赤べこちゃんバーガーなんてあったら食いたい、奥州陸奥国住まいの審神者なのであった。